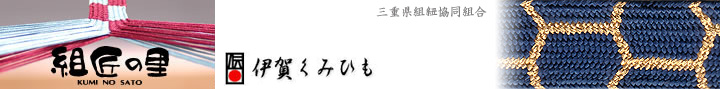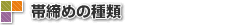
代表的な帯締め
※写真をクリックすると拡大します。
角台 |

|
四つ組
|
角台で組まれる組みの基本的なもので、四玉で組むのでこの名がついた。 |

|
八つ組 |
八玉で組む丸紐。四つ組みより組目が細かく、弾力性のある紐。 |

|
丸唐組 |
組み上げの技法により、組目の交差を外へ出しながら組む。 |

|
平唐組 |
丸唐組の応用、角台の代表的な組み方で、やや肉厚の紐。 |

|
鴨川組 |
江戸時代の文献にもその名が見られる日本独自の紐で、撚りが強よい。丸台でも組める。 |
丸台 |

|
冠組 |
主に冠の緒に使われたことからこの名がある。表が中央で半分に割れているのが特徴。 |

|
丸源氏組 |
色の違う矢羽根柄を交互に組み込んでいる点が特徴で、交ぜ柄の代表的な組紐。 |

|
洋角組 |
杉の葉が並んだような組目で、八つ組紐を芯にいれて組んである。 |

|
平源氏組 |
丸源氏を応用して平たく組んだ紐。肉が薄く、幅もあまり広くない。 |
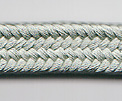
|
御岳組 |
角八つ組、洋角組を横に二本連結して組んだ紐。 |

|
唐組 |
矢羽根模様の笹波組の応用。笹波組の組み方をあるところで逆方向に組むことで菱形模様となる。 |
高台 |

|
高麗組 |
伊賀組紐の代表的な紐。唐組と並ぶ高級な平組で格調ある美しさをもつ。 |

|
貝の口組 |
貝の口のように固い紐ということからの命名。元来は太刀のの緒や下げ緒に使われた。 |
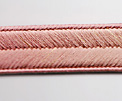
|
大和組 |
一方の表面がしゃず目になるように組まれているのが特徴。幅が広く肉厚。 |

|
笹波組 |
V字形の矢羽根模様が特徴。組み目が寄せ返す小波を思わせることからこの名がある。 |

|
内記組 |
安田組を二枚組み合わせた紐。高麗組よりも目がつんでいる。 |

|
畝打組 |
一枚高麗組を二本連結した紐。全体に畝のように見えることからこの名がある。 |
綾竹台 |
三段綾竹組 |
綾竹台にかける糸を三段に分けて組まれた紐。編物のような組目が特徴。 |
二段綾竹組 |
二段に分けて組むもので、この組み方は線を基調にした柄に特徴がある。 |
二段巻綾竹組 |
綾竹組に絹巻を組み合わせた紐。巻いた部分は別の糸を巻く。 |
手組台別による組台の分類(帯締めの種類)
平組
【高台】
高麗組、甲斐の国組、地内記組、綾高麗組、笹波組、大和組、竜甲組、藤波組、笹波唐組
【丸台】
唐組、平源氏組み、笹波組、平杉組
【角台】
平唐組
【綾竹台】
綾竹組、紅梅組、武田組、遠州組、小桜組
【重打台】
重打組、三好組
【内記台】
内記組、角朝組
丸組
【丸台】
丸源氏組、つくし組、丸杉組
【角台】
四ツ組、八ツ組、江戸組、加茂川組
角組
【丸台】
角源氏組、角杉組、冠組、御岳組
【角台】
洋角組
|